👉高田びわのす通信 TOP 👉大分市高田校区自治会 👉大分市高田校区まちづくり協議会 👉高田校区公民館
👉大分市高田の歴史
「高田村志」を意訳するにあたり<再度記載>
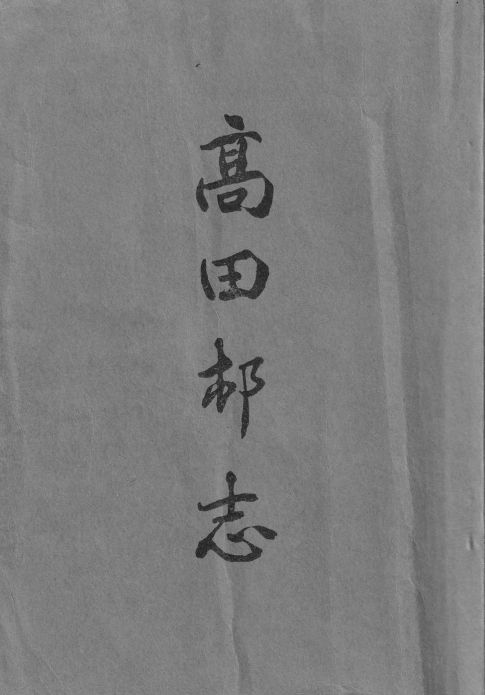
「高田村志」は大正九年に書かれた高田の歴史、地理、人物等を記した地誌であり歴史書です。「続高田村志」など高田の歴史についての書籍はこの「高田村志」をもとにしており、「高田村志」は高田の歴史のバイブルです。
この「高田村志」は臼杵市出身の考古学者、久多羅木儀一郎氏(鶴崎地区の多くの歴史書を書かれ郷土史研究に尽力された方である。)、中村壽徳氏、小手川又吉氏(後に公民館長、若葉幼稚園の初代園長、初代高田昭和井路組合長等をされる)の三人で編纂され大正九年6月10日に完成しました。鶴崎地区の小さな村の一つに過ぎなかった高田でこれほどの村志が発刊されたのは県下でも驚くべきものだったのではないでしょうか。
岡松甕谷
この「高田歴史散歩<16> 岡松甕谷」のほうがパンフレット的でわかりやすいかとも思いますが、元になった「高田村志」を意訳しながらできるだけ忠実に書いてみたいと思います。
👉岡松甕谷 高田の歴史散歩《16》
高田校区では高田地区の偉人として、(左から)毛利空桑、紀行平、岡松甕谷の三人を追悼して毎年三哲祭を行っています。昨年、令和4年11月に100周年記念を行いました。
👉ふるさと祭り・先哲祭

幼児の英異
※英異 非凡で優れている
岡松甕谷は大字丸亀の人、文政三年(1820年)正月十四日に生まれる。名は辰、字は君盈、通称を辰吾といい、後に伊助と改める。岡松家第六代の代官兼総庄屋
数右衛門(真友)の第二子にて、最後の庄屋であった俊助 (宇子棟、眞任という。)の弟である。甕谷と称したのは、丸亀の対岸百堂(現大分市種具百堂)の地にあった山の麓に、甕谷(かめのたに)という地名があったのがもとだという。
幼い時から営異で六歳の時にはすでに四書(「四書」とは『論語』『大学』『中庸』『孟子』の四つの書物です)を素読し、十四歳の時には漢詩を書いている。(漢詩は省略)



修学
叔父信甫(のぶすけ 通称を亀吉といい、父、数右衛門の弟) 高山彦九郎と親しくしており、いつも世の中のあまり知られていない興味ある話を聞いていたので、甕谷は早くから王覇の違いを知っていた。(甕谷は尊王愛国の気持ちが強かった)
王道 儒教で理想とした、有徳の君主が仁義に基づいて国を治める政道。
覇道 儒教の政治理念で、武力や権謀をもって支配・統治すること。
成童(15歳以上の少年 )の時に、熊本藩の時習館に入ろうとしたが藩が認めなかったため、憤慨して戻り、1836年甕谷17歳の時に日出の帆足萬里の塾に入った。萬里も深く甕谷の人格と才能を愛し、心を込めて教え育てようとし、甕谷もまた夜を日につぎ、力を尽くして勉学に励んだので、經術(けいじゅつ 儒教による統治の法。)に、文章(文を連ねて、まとまった思想・感情を表現したもの)に、すべてにわたり優れており、抜きんでて他の同胞をうわまわっていた。
かって、萬里の「窮理通」、「井樓纂聞」等を脱稿したので、門弟に命じて校訂させたり、漢訳をさせたが、常時甕谷の行文(文書の書き進め方)は最も流麗で、常に師友の推奨するところだったという。
<参考 甕谷19歳(1838年) 四月母亡くなる。12月父亡くなる>
遊学
弘化四年(1847年)二十八歳の夏、萬里に従つて京節に勉学に行き、同門の友だった霊山の宗士仁の別荘にとどまり、儒流(儒家の流派。儒学の流れをくむ者。儒者の家柄)を訪ねたり、、あるいは美しい景色を見て回ったりして静かにゆっくりとした生活をしていた。12月になると、京都を出て江戸に向かい、 安井仲平、 木下士勤等の諸士と交流する。甕谷は医学にも通じていたので、蘭方医竹内玄洞に迎へられ其の家に仮住まいしていたが、翌嘉永元年(1848年)になって、前から文武の士を愛した大番頭久貝因幡守に知られて、市谷加賀町なる其の道場内に住むようになる。当時甕谷は東坡(宋の文豪)の詩句からその宿舎を東雪舎と名付けた。
この頃からだんだん世の中が騒がしくなり、日出藩主は帆足萬里を起用して政務に当らせようとし、藩主から召還の命が来たので、甕谷も翌二年四月日出に帰り、萬里の弟子たちに監督、教授した。 この年、甕谷、この世の中に感ずるところがあり、叔父信甫の話を思い出し、七月承久記略の稿を書き始め、数か月で之を書き上げた。
熊本藩出仕
嘉永五年(1852年)師帆足萬里が亡くなった後、始めて熊本の時習館の居寮生(校内の寄宿舎に寝起きして学ぶ者 寮生)になったが、時既に学業に立派な業績を残しており、時習館の他の教授を圧倒する意気があった。
この頃、全國至る所で海防の論が盛になっており、熊本藩では幕府から出兵を命じられたこともあり、上下の騒動は一層激しいものだった。 甕谷はそこでたびたび藩の上に上書し警告をすることがあったが、その議論が他に抜きんでて優れており、普通の学生の域を超えているとして遂に藩の重職澤村西坡の知遇を受けるようになった。安政元年には經筵侍講(けいえんじこう 君主に対して学問を講じることまた人)に転じ、翌年には唐宋明清の(中国の歴朝)の律例に詳しかったことから獄曹椽(典獄)になり、ついで詮曹(せんそう 裁判長)となり、中小姓班(大名や旗本の下級家臣)に列す。安政三年藩主の参勤交代に従って江戸に行き職務に勤める。
翌年四月、熊本藩に戻るが(この時、北野恒子と結婚する)、此の頃から世の中がなお騒がしくなり、そのため藩命を受けて、あちらこちらに忙しく動き回った。このような時でも、甕谷は此の間にありても、甕谷は常に心を西籍にひそめ(儒学への思いか?)、文久三年(1863年)には、熊本壺井川上に家を構え、竹寒沙碧書屋(明治10年の西南戦争で焼失)と名前を付け、暇あれば入て、読書窮理(きゅうり 物事の道理、法則をきわめること。)に少しも休むことなく、また羽倉簡堂、河田猶興、長戸士謙、關思恭等の諸儒(多くの儒学者)と交友を持った。こうして藩に仕えること十三年、慶應三年(1867年)四十八歳の時に成山公子(長岡子)に上書し、病のため時習館を辞職する。
明治維新後の活動
明治維新後、(明治2年 1869年)抜擢され昌平校(江戸幕府直轄の学問所)教授となり、そのあと大學少博士となる、五十歳(満49歳)であった。全国から甕谷の名を聞いて学業を志したものは、加賀大聖寺藩士、倉知光謙等三十人余りだった。翌年七月に大學少博士を免じられ、更に太政官權少史(国家の最高機関の役職の一つ)に任命されたが、固辞して就かず、東京から高田に帰った。明治四年(1871年51歳 甕谷三男三太郎が生まれる のち京都大学教授になる )延岡藩の招きに応じて学問を教え、課業の合間に、英文の勉強をし「滞滝中窮理解環一巻」、「譯分彙編数巻」の翻訳がある。
明治六年十一月に病で辞職し、熊本の旧家に戻り帰臥(きが 官職や世間で目立つ地位から退いて(故郷にもどり)、静養・農耕などの、自然を友とするような静かな生活に入ること。)自分の塾を開いた。
こうして二、三年、東京の友から頻繁に上京するよう誘いがやまず、ついに明治九年(1876年 57歳)二月に上京し紹成書院を創設して塾を始めた。書院の名は全国に広まり学んだものは数千人に及ぶ。川田甕江と並んで、東都の二甕と言われた。 明治15年(63歳)東京大學文學部教授となり明治 二十二年(1889年 70歳)東京學士会員に推薦される。
甕谷晩年
甕谷は後年、蘭学から英学に入り、西籍には特に熱心で、以前書いた窮理解環、澤文彙編のほか、西客問答等の著譯があったが、傍らまた東西の史乗(しじょう 歴史の記録)をやり遂げようという気持ちもあり、内大臣三實美に上書して、気持ちを建白したが顧みられなかった。そこで気持ちを奮い起こし自ら文を書き、東瀛記事本末二十卷を著し、逐次西洋各国をもやっていこうとする。しかし、世の流れが一変して、人々が洋風に心酔するようになり、それに納得できず、それ以来、西洋のことは論ぜず、好んで論語を講じ紹成講義を著わす。これからは漸く世間に背を向け、家計は昔のようではなくなったが、困難や貧しさにも何も変わらず、彼自身安らかに落ち着いていた。甕谷はまた叙事文にも力をいれ、漢譯常山紀談の編がある。 常に自らに言い聞かせていたのは、文書のうまい下手は別にして、文書では自分のように学問などを着実に研究したものはいないと。門人中江篤介(中江兆民)の書物にしても、甕谷がこのような心持で教え育てたからである。
晩年 甕谷が肺を患いて病気の状態が次第に重くなると、一日細川十洲(幕末の土佐藩藩士、明治・大正時代の法制学者・教育者)が來訪し、梅花数枝を贈ると甕谷はとても悦び、床の上に寝たまま 漢詩を吟じた。
調朋贈我一瓶春
數朶瓊英映壁新
自咲衰残瀕死日
得爲渓上看梅人
この時に十洲が、瀕死の二字は何とか改めるべきだと言ったが、べしさいひしに、甕 甕谷は、これは写実であるといって改めなかったという。
明治二十八年(1895年)二月十八日、七十六歳にて築地の住まいで亡くなる。
三月三日青山墓地に葬り、忌み名として文靖先生という。長男(上の二人は誕生後亡くなっている)は参太郎法學博士である。二男は匡四郎工學博士で、子井上毅の養子となる。
次回「高田村志」を読む は 第4章 1・閼伽池 2・西海寺磧 3.清寧場 です。
👉 第4章 1・閼伽池 2・西海寺磧 3.清寧場

