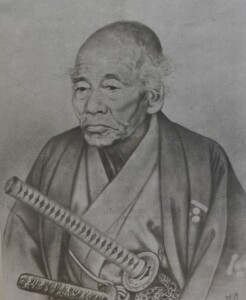豊後の国は明治まで大友宗麟の影響か大友家のみで豊後の国を支配していたと考えてしまいます。しかし。
【大友宗麟の時代】
大友氏の大友能直(よしなお)が鎌倉幕府に守護代として幕府成立(1192年)後九州に派遣される。そして豊後の国の初代当主なり、以降、大友氏が関ヶ原があったころの江戸初期まで400年ほど続きます。最盛期には豊後・筑後に加え豊前・肥前・肥後・筑前の6ヶ国と日向・伊予の各半国を領有していました。
図面【大友氏の最盛期の領域】
薩摩と2分するほどの大名になっていましたが、大友家の内部抗争、他の九州勢の反旗により危機的状況まで陥っていきました。そして市内では薩摩との戦いで(戸次川の戦いが有名です)苦戦し敗北寸前まで行きました。その薩摩との戦いのときに、高田の多くの古くからあった寺院やお寺(若宮八幡社、常行天満宮、上徳丸天満宮、補陀寺、興聖寺)が消滅しました。府内は占領され焼かれてしまいました。豊臣秀吉の支援を受け、滅亡せずに終わりましたが秀吉に臣従しました。そして秀吉は九州征伐として薩摩藩を破ります。1586年~1587年) 《マメ知識 1582年には今の大河ドラマになっている本能寺の変が起こっています。》
しかし、天正15年(1587年)宗麟は津久見に隠居し信仰生活をしながらここで58歳で亡くなります。墓地もここにあります。(以前撮った写真を捜索中)
次の当主の大友義統(よしむね)は文禄の役における敵前逃亡をとがめられ、文禄2年(1593年)に秀吉の命令で豊後領を改易され大友氏の支配は終わります。そしていったん隠居していたのですが、関ケ原の戦い時に毛利輝元に支援され、東軍細川忠興らの領地となっていた旧領の回復を計画します。しかし石垣原の戦い(別府)において黒田孝高(黒田如水・ 黒田官兵衛でよく知っていると思います)の軍に敗れて降伏し幽閉の身となり53歳で亡くなります。
しかし大友家は嫡男 大友義乗(よしのり)が旗本として徳川家に召抱えられ、鎌倉以来の名家として続きます。
第2回 江戸時代 小藩分立 高田は細川藩

上記のように大友氏滅亡後大分は多くの藩に分断してしまいました。(詳細は機会があればUPしたいと思います。)そしてその中でまた細かく分断したのが、わが高田周辺です。(高田は肥後細川藩です)
分かりますか。まず、鶴崎は三佐(岡藩領) 家嶋(臼杵藩領) 千歳(延岡藩) 乙津(天領)と入りくんでいます。高田周辺も 高田風土記(1800年 文化年間)によれば 臼杵藩は 丹生 岡 延命寺 金谷 毛井新田 横尾 森村 森町村 大津留村 毛井村 等 幕府領松岡村になっています。(知られている村をあげています)
それ以外の鶴崎、大在、坂ノ市、佐賀関、野津原、竹中などは、肥後熊本藩の飛び地でした。(図の青い部分です)
加藤清正は肥後藩を治めることは決まっていましたが、「いざ、大坂!」の時、最短で大阪に向うアクセスとして豊後に飛び地を確保したといわれています。鶴崎はその中心に位置付けられ、熊本藩の瀬戸内海に向っての玄関口として重要な役割を果たしました。
参勤交代では、熊本から阿蘇を越え野津原を通り、鶴崎から海路で大阪、江戸へ向かいました。
常行に岩丸とありましたが、細川藩が船で川を下った船を置いていたと聞いています。
他の藩が河口に飛び地を設けたのも、臼杵藩や岡藩が犬飼にあった川の港から河口まで米などの物資を運搬、集積する場所が必要であり、また参勤交代の港湾地の確保が必要でした。
また、竹中のお寺と高田のお寺の行き来があったのもこの細川藩領だった関係かもしれません。(竹中の勝光寺を上徳丸の能仁寺が再建に協力する 歴史散歩⑰ 能仁寺に記載)
そして、高田は細川藩領として発展していきます。
高田周辺の藩の区分図


[図面 大分市HP参照]
第3回 大友から加藤清正へ
時代が前後しますが、大友氏末期を再考してみたいと思います。戦国末期の九州は、豊後の大友氏、薩摩の島津氏、肥前(佐賀)竜造寺が主に支配していました。しかし、薩摩、大隅を統一した島津は北上し、大友氏と勢力争いをするようになりました。そして両者は1578年宮崎の日向を争って戦います。耳川の戦いが有名です。そしてこの戦いで大友氏は大敗北をきっします。大友宗麟は豊臣秀吉に直接に会い、援軍を頼みます。そして島津との停戦を受け入れます。しかし、勢いの乗っていた島津氏はそれを受け入れず1586年には豊後にも進出してきます。そして島津の通り道である戸次地区では、今でも利光地区がありますが、そこを納めていた利光氏の牙城であった鶴ヶ城の戦い、戸次川の戦いがあります。戸次川の戦いでは四国から長曾我部氏が秀吉の命令で援軍に来るのですが敗北します。この戦いについて調べるのも面白いかもしれません。
長曾我部氏の慰霊碑


戸次川の戦いの古戦場跡地


島津の勢いを止めることのできなかった大友軍は、高崎城(高崎山には土塁の跡が残っています)や、宇佐方面に後退していきます。大友宗麟は臼杵に移動していました。しかし、豊臣秀吉が大軍で九州に進出してきたことにより、島津は薩摩に戻っていきました。そして間もなく秀吉に降伏しました。この戦いの後、大友氏は豊後の国のみの支配を許されます。大友宗麟は次の年、隠居先の津久見で58歳の生涯を終えます。
なお、先の府内の戦いのときには、鶴崎地区も戦いに臨んでいます。鶴崎城では大友氏の家来、吉岡氏の妻、妙林尼(みょうりんに 吉岡氏は先に述べた耳川の戦いで戦死し、夫をともらうために出家していた)が、島津氏の16度の攻撃、三カ月間にも及ぶ攻防に耐え、最後は島津との和睦に応じ、全員の生命を保証するということを条件に開城しました。その時には、薩摩と酒を酌み交わしたともいわれています。 (薩摩側も先へ進めないこと、吉岡側も食料が尽きていたことが和睦を勧めたといえる)また、ここには、多くの高田の人が登場してきます。当時、高田は鶴崎城主吉岡氏の配下にあり、徳丸氏、中村氏、向氏等一族の物が多く参加し手柄を立てています。
妙林尼像(鶴崎校区公民館前)


[鶴崎城について]
現在の大分市立鶴崎小学校・大分県立鶴崎高校の場所には、かつて鶴崎城(つるさきじょう)があったという。
この鶴崎城の城主は吉岡鑑興(よしおかあきおき)妙林尼の夫である。この吉岡家は、当時、豊後一帯を統治していた大友氏の側近の一族で、もともとは父である吉岡長増(よしおかながます)が鶴崎城を築城したといわれている。
(※鶴崎城についてはこれまでは上記の意見が支配的であったが、この地の遺跡調査によりこの地ではなかったのではないかという考えも出ている。)
鶴崎城跡地(鶴崎小学校、高等学校の跡地)


しかし、この大友氏の支配も長く続かず、第1回で述べたように豊臣秀吉の逆鱗に触れ、改易されここに大友氏の支配は終わります。そして1601年に熊本の加藤清正により肥後藩に組み込まれます。
では、それまでの熊本はどういう状態だったのでしょうか。熊本は長い間(戦国前期)、南部の相良氏、北部の菊池氏、東部の阿蘇氏の三氏によって治められていました。しかし、力のつけてきた大友氏により菊池氏は平定され阿蘇氏は影響下に入ります。そして先に述べたように島津氏は北上し、相良氏、阿蘇氏をも平定していきます。大友氏も破り九州平定寸前であった島津氏も、豊臣秀吉の進出によりその夢も破れてしまいます。そしてその熊本を治めたのが秀吉から統治を命じられた富山城主の佐々成正です。しかし、改革を急いだ結果、肥後の国人一揆(1587年)が起こり、その責任を取って自害しています。そしてそのあとを継いだのが小西行長と加藤清正でした。小西生長は中南部を、そして加藤清正は北部を治めました。
しかし、この二人の明暗を分けたのは関ケ原です。
第4回 加藤家から細川家へ
第3回で書きましたが、肥後の国人一揆(1587年)が起こり、隈本を治めていた佐々成正がその責任を取って自害しています。そしてそのあとを継いだのが小西行長と加藤清正でした。小西生長は中南部を、そして加藤清正は北部を治めました。その後、1592年~1597年の朝鮮出兵(文禄・慶長の役(ぶんろく・けいちょうのえき)があり、豊臣秀吉の死によって撤退し終わりを見せます。
豆知識ですが、清正が朝鮮出兵の際、もち米や水あめ・砂糖などを原料とした長生飴というものを非常食として常備しました。これが今でも有名な朝鮮飴です。
豊臣秀吉が亡くなった(62歳)まもなく、1600年関ケ原の戦いが始まります。
しかし、関ケ原の戦いには加藤清正は出てきません。どうしてでしょうか。それは関ケ原の前年に加藤清正は、薩摩を治める島津氏の筆頭家老・伊集院氏が起こした「庄内の乱」で伊集院氏を支援したことが徳川家康に知られ上洛を禁止されてしまいます。徳川家康は乱の収拾をはかっていたためです。このため、加藤清正は「会津征伐」から始まる「関ヶ原の戦い」に参加することができず、「黒田官兵衛」と共に、九州の西軍勢を攻めることしかできなかったのです。関ヶ原の戦いには参戦できなかった加藤清正ですが、小西行長や「立花宗茂」(たちばなむねしげ)の城に侵攻し、九州の大部分の西軍勢を打ち破りました。
肥後北部25万石を領有していた隈本城主加藤清正は、関ヶ原の戦いの戦功により小西行長の旧領を獲得し、また豊後国内にも鶴崎など2万石を加増され、52万石を領したことにより熊本藩が成立しました。豆知識ですが、これまで隈本といっていたのを熊本に変えたのは加藤清正だそうです。熊本城落成の折、隈本より、熊本のほうが勇ましそうだからと言ったそうです。
熊本藩(肥後藩)といえば加藤清正と言われますが、実際には清正が肥後国を治めていたのは、天正15年(1587年)から慶長16年(1611年)の期間だが、朝鮮出兵等もあって実際に熊本に居住していた期間は延べで15年程です。しかし、いまでも熊本では「清正公さん」(せいしょこさん)と呼んで人気があるし、鶴崎の法心寺や二十三夜では今なお加藤清正を祀っています。
加藤清正像







加藤清正は、関ヶ原の戦い以前から着手していた「熊本城」の築城を続け、1606年(慶長11年)に完成させます。、当時「日本一の名城」とも言われ、現在も「日本三名城」のひとつとされる立派な城です。
また、加藤清正は、肥後統治でも手腕を発揮します。城下町の整備・治水事業・農業政策・商業政策を推進し、肥後を豊かな国にする基盤を作りました。領有地の鶴崎には鶴崎城跡地に御茶屋(領主の宿泊所、諸役所)や、法心寺、船着場(港 現鶴崎支所周辺)を設けています。また、高田には溢流提が加藤清正によって造られたといいます。昭和10年代に護岸工事で消滅してしまったそうです。
また、川添には加藤清正による護岸工事跡(四国の青石を使って作ったといわれています。大潮の干潮時に出現するそうです。金谷水門200m上流) 加藤清正の治水事業の一角が残っています。
その加藤清正も1611年には徳川家康よりも5年早く50歳で亡くなります。その死については毒殺や毒まんじゅうを食わされた、などの伝説もあります。
そして清正が亡くなった後、三男の忠広が肥後国熊本藩2代藩主になります。しかし、多くの理由により加藤家の熊本統治は終わってしまいます。
忠広が若すぎ、その統制も困難になっていました。それが家中の対立を招き、藩政の停滞・改易につながったともされています。
また、加藤家が豊臣家と親族関係があったこともあり幕府がつぶしたかったとの説もあります。
1632年5月22日、江戸参府途上で忠広は幕府より入府を差し止められた上、改易を宣告されました。肥後熊本藩54万石は没収、忠広は出羽庄内(山形県)の酒井家にお預けとなります。
加藤家による45年の熊本藩統治はここに終わります。わずかな期間の中にも多くの加藤家の業績が鶴崎地区にも残されていると思います。
この後、加藤家をついで熊本に入ってきたのが細川家です。
【豆知識 鶴崎の御茶屋】
現在の鶴崎小学校と鶴崎高等学校の一帯にあり、一辺が100m四方くらいのほぼ正方形の屋敷で周囲には堀が廻らされ、その中に都会所、銀所、銀蔵、武器蔵。郡代宅、藩校なども併設され、熊本藩の豊後支所として機能していました。
加藤清正を祀っている法心寺
第5回 細川藩時代
工事中
鶴崎市と旧藩名
以前、高田の歴史をHPに挙げた際、小藩の区分がわかりにくい、との指摘がされた。確かに、高田の歴史をみていると、旧鶴崎市全体が掴めていないと理解しづらいことがわかった。
県図書に鶴崎市発行[昭和32年発行]・ 久多羅木儀一郎著 の[鶴崎市史]があり、大分市と合併する前の昭和29年当時の地名と藩の区分が載せられていたのでそれを参照させていただいた。
*
鶴崎市は1954年(昭和29年)3月31日鶴崎町・松岡村・高田村・明治村・川添村が合併して発足。
上記のごとく、藩政時代には、旧鶴崎市に凡そ40ばかりの小村が分立し、幕府領を含めて五藩によって分割されていた。
| 旧町村名 | 現大字名(注1 昭和29年) | 藩政時代の村名 | 所属藩 |
|---|---|---|---|
| 鶴崎町 | 鶴崎 | 鶴崎町 | 熊本藩 |
| 〃 | 国宗町 | 〃 | |
| 鶴崎 | 寺司町 | 〃 | |
| 鶴崎 | 鶴崎村 | 〃 | |
| 小中島 | 小中島村 | 〃 | |
| 三佐村 | 三佐 | 三佐 | 竹田藩(岡藩) |
| 海原 | 海原村 | 竹田藩(岡藩) | |
| 家島 | 家島村 | 臼杵藩 | |
| 桃園村 | 乙津 | 乙津村 | 幕府領 |
| 三川 | 今三川村 | 〃 | |
| 〃 | 現三川村 | 延岡藩 | |
| 千歳 | 千歳村 | 〃 | |
| 山津村 | 〃 | ||
| 別保村 | 皆春 | 中島村 | 延岡藩 |
| 門田村 | 〃 | ||
| 森町 | 森町村 | 臼杵藩 | |
| 森 | 森村 | 〃 | |
| 明治村 | 小池原 | 小池原村 | 臼杵藩 |
| 猪野 | 猪野村 | 〃 | |
| 横尾 | 横尾村 | 〃 | |
| 葛城 | 葛城村 | 大部分 延岡藩 | |
| 〃 | 南西部 竹田藩 | ||
| 〃 | 西一部 臼杵藩 | ||
| 高田村 | 関園 | 堂園村 | 熊本藩 |
| 関門村 | 〃 | ||
| 常行 | 常行村 | 〃 | |
| 南 | 南村 | 〃 | |
| 下徳丸 | 下徳丸村 | 〃 | |
| 丸亀 | 上徳丸村 | 〃 | |
| 〃 | 亀甲村(上徳丸の枝村) | 〃 | |
| 鶴瀬 | 大鶴村 | 〃 | |
| 〃 | 鵜猟河瀬村 | 〃 | |
| 松岡村 | 大津留 | 大津留村 | 臼杵藩 |
| 毛井 | 毛井村 | 〃 | |
| 松岡 | 真萱村 | 幕府領 | |
| 松岡村 | 〃 | ||
| 成松村 | 延岡藩 | ||
| 池上村 | 〃 | ||
| 川添村 | 広内 | 臼杵藩 | |
| 宮川内 | 〃 | ||
| 種具 | 百堂村(関門の枝村) | 熊本藩 | |
| 中ノ瀬村(関門の枝村) | 〃 | ||
| 鶴村 | 〃 | ||
| 迫 | 迫村 | 〃 |
かえってわからなくなった人がいるかも。