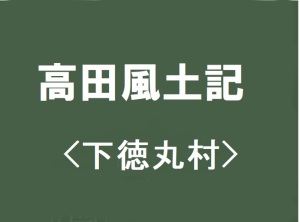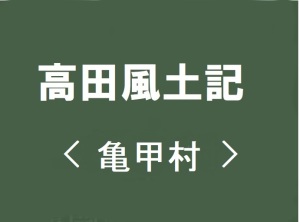高田風土記(訳) 前回のつづき
なお、前回(堂園、常行)の訳は 安部光太郎先生 、関門以降は阿部勝弘氏の訳になります。
読む前に
高田風土記は細川藩が江戸時代の末期に肥後藩領だった高田手永(旧鶴崎市に近い領土)について詳細に調査した報告書です。
その中で高田地区に関係するところを抜粋してみました。
なお、当時高田荘といわれたところは、高田 をはじめ、鶴崎、三佐、桃園、別保、明治、日岡、東大分、大在字志村、川添字迫、鶴村の 1町9ケ 村に亘る地域でした。
高田風土記ついては下記を読んでください。
※青文字で注釈を入れていきたいと思います。
上徳丸村
鶴崎御茶屋から南にあたり、関門村・下徳丸村を通って一里
程離れている。
○東から南をまわっては大川を境にして、東は百堂村、そこ
から南にかけて臼杵領金谷村と境になる。 そこより西に
は臼杵領毛井新田村にも境になる。西は亀甲村と下徳丸
にも境となる。 北にはすべて下徳丸と境である。およそ
東西は五丁半程で南北は六丁程の地である。
田畑賦税(この項原文のまま)
畑二十二町三反九畝余、高二百二十五石七斗余、物成百四十
石五斗余、免は塘内六ツ三分余、塘外は四ツ一分余、
この分は本方にして、この外新地分高三石八斗余、畑畝数は
新地・諸開畝物等にて一町五反余りありて、上納米三石二斗
余運上銀二十八匁余なり、御年貢は銀能にて前の村に同じ
である。
土地糞壌
畑地多く村の三方面にあって、多くの土地は真砂土で耕作に
適すが、土性は深く堅く耕すには労するし、赤ぎちの土地で
あり耕すには苦労する。またごみ土まじりの所もあって、柔
らかではあるが、地質は劣っている。
○土手のそばは小砂まじりで地は浅く、
○土手外は川辺であり、洪水毎に上の方の土を洗い取るの
で、小石や小砂交じりになって極めて地質は悪い。
○肥料はすべて前の村に同じである。
戸口牛馬
竈は五十軒ある。 男女二百人余、馬は十一疋・牛は一疋です。
外に亀甲村の百姓がこの村の内に十軒住んで居る。
○村内には瓦葺の蔵二軒あり、土蔵は一件ある。
○特高三十五石から十五石までの百姓は二軒、五石から三
石まで十一軒、二石から無高までの百姓三十七軒ある。
○高敵を人口で割ると、一人につき高は一石一斗余・畝数は
一反一畝余にあたる。
○髙田手永御惣庄屋の会所がある。
課役
助水夫株一人ある。年々御参勤の時、出勤する。その外は
前項の村々と同じである。
神祠寺院
天神社の小さな祠が一ヶ所ある。
能仁寺[禅宗で丹波国永澤寺末寺、寛文五年〕妙應公
(細川綱利)の建立で、耶蘇教(キリシタン)の者の教化の
ために雲歩和尚を命じました。今に至るまで、月俸として十
五口を支給され、九曜の御紋を賜りました。境内は二反で御
年貢免除地です。檀家は五十軒ある。
山林原野
東南にある川の土手側に一町六反四畝余、村内の人家の間
にも御薮が一反三畝ある。 東の川辺にわずかな河原がある
だけで、薪や秣(まぐさ)に付いては前の村と同様である。
池水利
この村の南から東に大川が流れている。この村から亀甲や
大鶴にかけては、洪水の時、川の水の勢いが強いので、堤防
も特に高くしており、根張りも広く取っている。村内には水
吐けの水道が二ヶ所ある。
○村内には井戸が四十余〔深さは水際まで二間から二間半
まで〕あり、水の勢いは強い。
街道
村内には鶴崎からの往還があって、亀甲村まで通っている。
さらに、百堂の渡しへつづく道もある。
産物
堂園村の内容と同じである。
餘産
この村には日雇・他所稼ぎに出る者もあり、女は縁り布を織
るか、其の外に柚(そま)の商いを生業にしている者もいる。
※杣(そま)とは
樹木を植え付けて材木を取る山。杣において働いている人のこと。
近世・近代の日本では転じて林業従事者一般の意味で用いられるようになった。
風俗
この村には富裕の家はないが、ほかには堂園村の内容と同
じである。