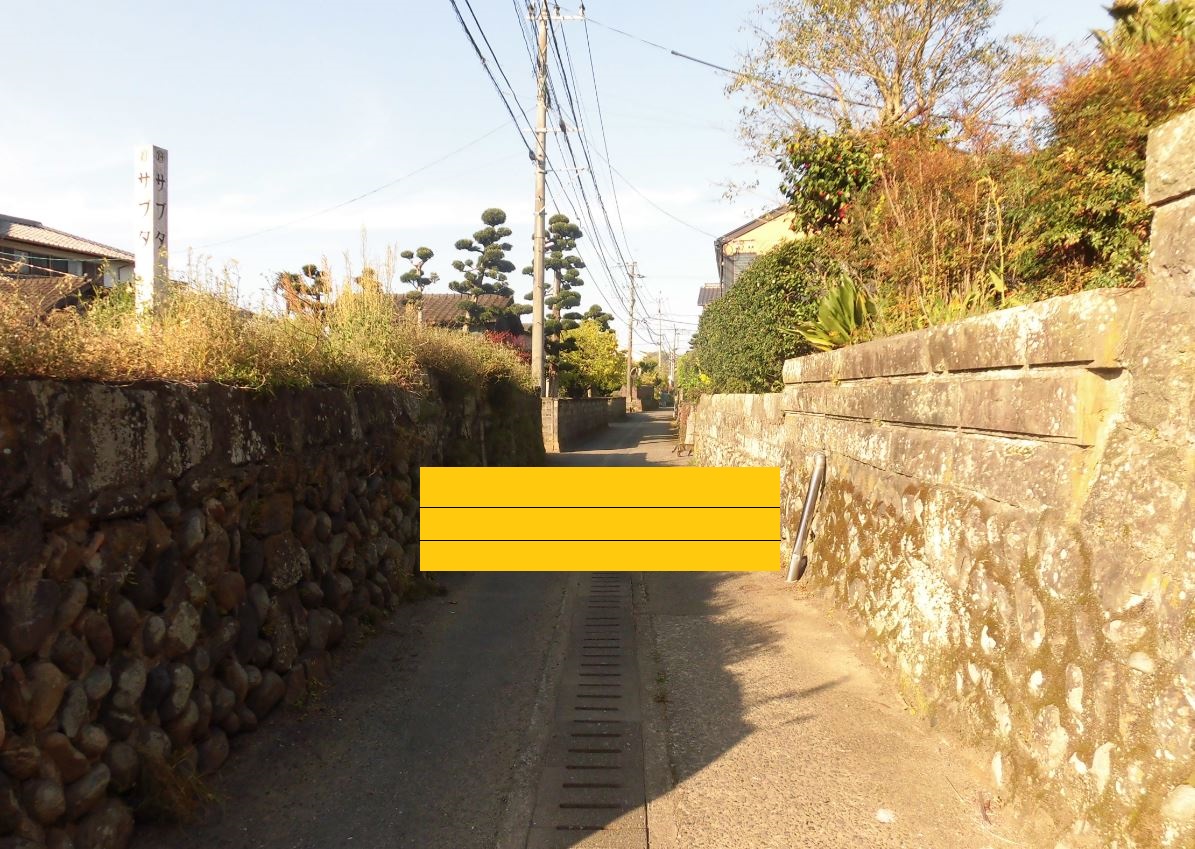高田校区歴史マップ

地区別 歴史マップ〈説明番号の確認〉
下記の図から番号を探し、その番号の歴史標柱を訪ねてください。

歴史マップ 〈関門自治会・南自治会〉


歴史マップ 〈鶴瀬・丸亀・下徳丸自治会〉


歴史マップ 〈常行・堂園自治会〉

歴史マップと歴史標柱
高田校区歴史標柱・31ポイントの紹介(スマホ&PC) (見たい歴史案内は下記の表にある👉をクリックしてください。)
① 奨順社の碑
関門出身の小手川善次郎氏は昭和3年(1928)、 地区内に有する広大な宅地、畑地及び高田銀行株券を高田村に公共施設、 並びに社会福祉のために寄付しました。 村長岡松準平はこのことに感激し 「財団法人奨順社」を設立しました。 この碑は高田公民館敷地内にあります。


⑥ 補陀寺
👉 補陀寺
慈雲山 補陀寺ふだじ (臨済宗)補陀寺は天平勝宝7年(755)に天台宗の寺院として開かれた高田では最も古い寺です。
応徳元年(1084) 失火によって堂字は炎上しましたが、国主大友能直が頭領を寄進し七堂伽藍を建立したといわれています。 天正の兵火以後臨済宗済宗に改宗し京都妙心寺派に属して現在に至っています。。


⑦ 雨水排水ポンプ場
雨水排水ポンプ場
平成16年(2004)5月に内水対策として排水ポンプが設置されて平成17年
(2005)の台風14号でその効果が実証され、 今まで苦労していた水門の開
閉の心配がなくなりました。
場所と能力は
関門に設置、 大野川へ毎秒7屯
常園に設置、 乙津川へ毎秒9屯


⑧ 水難横死生徒の碑
明治26年(1893)10月14日洪水で横死した児童八名の追悼のために旧高田小学校のあった下徳丸字屋敷に建立され、その後学校の移転に付属して現在の高田小学校の地に移されました。碑文は毛利莫(さざむ、 毛利空桑の3男)


⑨ 筒井嘉右衛門の墓
筒井加右衛門の墓 ( 河童伝説)加右衛門は高田代官所の代官兼惣庄屋で槍の達人でもありました。 大事な茄子を盗んだ河童を槍で突いたため、 翌日百堂の渡しを渡ろうとした加右衛門が多勢の河童に襲われあえなく命をおとしたという伝説があります。


⑩ 興聖寺
鳳林山興聖寺 (臨済宗)
興聖寺は、 妙心寺派に属しています。 嘉慶元年(1387) 別保大字森村曲の手
(現在の金の手)に創建され、領主大友家より寺領を給わりました。 その後、
たび重なる火事により常行の字権大など4回の移転を経て現在地に移りました。


⑪ 大野川高田地区河川防災ステーション
現在上徳丸川添橋横に市の防災対策として防災センターが設置されています。 非常の際のために砂、ブロック、その他の品々が常備され、 詰所、 会議室
各連絡設備、 ヘリーポート等があり、災害時の活躍が期待されています。
(平成11年 (1999) 3月24日業務開始)


⑫ 学校発祥の地
明治6年(1873)8月15日上徳丸中村寿八郎の家塾明倫堂を高田村が引き継ぎ同所中
村半次郎の屋宅を借り入れてここに移し明倫学校と命名して開校しました。これ
が高田小学校のはじまりです。


⑭ 上徳丸 道標
道標 (臼杵街道)
上徳神社前から南に向かうと三叉路に臼杵方面を示す道標があります。 金谷の渡しに通じる大事な街道でした。


⑮ 上徳丸天満社
上徳丸天満社は太宰府天満宮の御分霊を勧請して祭られました。社殿はもと宮前屋敷と言う所にありましたが天正の兵火にかかり焼失しました。 安永3年(1775) 金谷渡し場北方の堤上に社殿を新築しましたが、明治26年の大洪水で倒壊し、現在地に造営遷祀されました。


⑯ 高田会所跡(岡松甕谷生誕の地)
熊本藩では「手永」 という行政区画に御代官兼御惣庄屋を置いて一切の民政をおこなわせていました。高田手永は高田8ヶ村を含める24ヶ村に及びました。 高田会所は高田手永における役所つまり代官所です。 細川家が藩主になってこの制度が置かれました。


⑰ 能仁寺
瑞光山 能仁寺(曹洞宗)能仁寺は神奈川県鶴見総持寺の末寺に属しています。 寛文5年(1666) この地におけるキリシタンに対し改宗を進めるために熊本より行厳禅師雲歩和尚を派遣しました。 雲歩は熱心に教化につとめキリシタンを根絶したために、藩主はその功を賞して新たに堂宇を建立しました。


⑱ 閼伽池
閼伽池昔若宮八幡社が此の地に鎮座していた頃に、明護院という修僧が社僧として奉仕し朝夕(神仏に供える水のこと)をこの池から汲んで神前に供えていました。このことから閼伽池と呼ばれるようになりました。 「馬場」という字名も若宮八幡の馬場からきたものです。


⑳ 宝塔様
| 宝塔様 (堰堤碑 ) 堤防の決壊により田畑、家財を流失、又溺死した人々を思い悲しむ声を聞いた常仙寺住職日宣は、首藤道英、道猛父子と語らい建立した、 一字一石の法華塔です。 (石の数は 69,384個) 碑文は毛利空桑74才 (明治3年 1870)に撰したとある。 |


㉑ 水難慰霊碑
明治26年(1893)の大洪水で水死した鶴瀬78人の供養に再建されました。 元は大野川の堤防上にありましたが、 昭和18年の台風で流失しました。
ところが建設中の鶴瀬自動車学校の建設現場から碑の一部が出土し地元と自動車学校と相談の上再建されました。


㉒ 一乗寺
開山一乗寺(日蓮宗)一乗寺は、鶴崎の法心寺末寺です。 寛文2年(1662) 法心寺三世守玄院日達が本村信徒と相談して創建しましたが、 その後200年を経、堂宇が著しく荒廃したので、安政6年(1860) に至り住職日歓がこれを再建しました。


㉓ 鶴瀬道標
鶴瀬一乗寺から200mほど下ったところにある道標は大分や熊本、小倉、 福岡までの距離、近くでは丸亀村、 明治村までの距離が表示されています。 明治の中期に建てられたもののようです。


㉕ 銀行跡
高田村大字南にありました銀行は高田実業銀行と称し、大正9年(1920)に設立されました。 本店は首藤宝吉宅に置かれ大分市に支店をもっていました。
また、挑園、明治、 松岡にそれぞれ代理店がありました。 昭和17年(1942)8月大分合同銀行に吸収合併されました。


㉗ 毛利空桑の墓
空桑は寛政9年(1797) 大字常行に生まれました。
脇蘭室、 帆足万里など多くの学者に学び、 また、 いろいろな武芸にも励みほとんどが免許皆伝のうでまえでした。
家塾知来館で育てた人は1000人を超すといわれています。


㉘ 常行神社
常行字井樋ノ口に鎮座する常行神社は、 太宰府天満宮の御分霊を仲摩五兵衛という人が歓請したと云われています。
元亀 (1570~1572) のころには字初穂田にあり広大な社地と3つの僧院を有していましたが、その後天正の兵火にかかり、万治 (1658~1660)のころ現在地に遷座しました。


㉚ 常仙寺
👉 常仙寺
雲鶴山 常仙寺(日蓮宗)
常仙寺は日蓮宗京都本国寺の末寺で、 正保元年(1643) 高田の刀匠藤原行長の喜捨に基づき学泉院日泰が建立しました。
当初は白頭山常仙寺といっていましたが、2世日長のとき鶴崎法心寺3世日達と両寺一山の契約を結び山号を法心寺と同一の雲鶴山を称するようになりました。