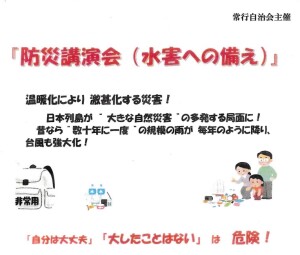前書き
高田公民館の資料室にある書類を公民館に見せていただきました。
ほんの一部を見せて頂いたわけですが高田の歴史に興味がある者には宝の山にみえます。
この資料を少しでも多くの高田の人たちにも見てほしいと思い、このホームページを通じて公開していこうと思います。
資料はあまりにも多いため、時代や内容についてバラバラですが手あたり次第にアップし、その整理は後日にしようと思います。
高田の歴史
1・先史時代
考古学上からみた高田
私達の郷土高田は大野川本流と分流乙津川に囲まれ、南北3㎞、東西1㎞、面積三.五㎢の大野川デルタにある輪中である。
この高田地区を中心としたデルタ地域では、いったん大水になると、氾濫して、大きな被害を与えていた。このような地形、環境であるから地区周辺で見られるような考古学上の遺跡や遺物は現在まで見聞されていない。
しかし別府湾の後退や弥生式土器文化時代以後は、明治、松岡、川添、大在の丘陵遺跡・文化から想像する時、 大野川氾濫後の肥沃な土地を先史時代といってもいいだろう。先進地域のような定着した姿は見られないが、おそらく作付け、収穫の時期に周辺の丘陵土着民が舟や浅瀬を利用して農耕が行なわれ、次第にその不便と建築技術の向上等によって、しの倉から住宅へと定着した生活へと発展したのではなかろうか。 又それらの位置も自然堤防など比較的高所を利用し、或いは溝を掘り、その盛土の上に倉庫、住宅を建て、現在郷土でみうけられる輪中建築様式へ発達したことだろう。
2・国府時代
大分(碩田)の地名の起り
碩田
◆ 県名の由来 「大分ガイドより」
「豊後国風土記」は、”おおいた”について景行天皇に由来を求めています。天皇がここに来たとき「広大なる哉、この郡は。よろしく碩田国(おおきた)と名づくべし」とし、これがのちに”大分”と書かれるようになったといわれます。
しかし、実際の大分平野は広大とは言いがたく、むしろ地形は狭く複雑であり、「多き田」→「大分」との見解が最近の定説です。これが”とよのくに””おおいた”の由来です。
この時代初期の頃の事ははっきりしないが大分平野や大分川、大野川の沿岸、丘陵地帯に早くから人が住み、その中で勢力の強いものが土豪として周囲に君臨していたと思われる事は、その周辺各地に現存する古墳、横穴、採取発掘される石器、土器、石棺等遺跡や物で知ることができる。しかし高田地区では先にも述べたようにこれら遺跡、遺物らしきものも見聞されていないが、日本書紀や豊後風土記等の古い文献から郷土を調べてみよう。
豊後風土記に、
「昔者(むかし)、纒向日代宮に御宇天皇、豊前国京都の行宮より此の郡に幸し地形を遊覧して嘆き曰く「広く大なる哉、此の郷、碩田(おおきた)の国と名づくべし」とある。これが碩田(後に大分とかく)の地名の起りとされている。それでは、高田郷の地名について調べて見よう。
豊後国志(巻之四)に、大分郡の郷を九として笠和(かさわ)、荏隈(えのくま)、賀来(かく)、阿南、植田(わさだ)、津守、判田、 高田、戸次の名を掲げ、次いで村の項に下記の四十村をもと高田郷に所属させたと記している。即ち
今津留・中津留・鼻津留・牧・萩原・(以旧東大分)
新貝・原・向原・高松・(以上旧日岡)
山津・本三川・今三川・乙津・千才・(以上旧桃園)
三佐・海原・家島・(以上旧三佐)
国宗・鶴崎・寺司・小中島・(以上旧鶴崎)
門田・中島・森町・森・(以上旧別保)
小池原・葛城・横尾・(以上旧明治)
大津留・亀甲・南・鵜猟川瀬・常行・上徳丸・下徳丸・関門・堂園・(以上旧高田)
津留・迫・(以上旧川添)
志村(以上旧大在)
である。
郷は古く大化・大宝の制によって置かれた所のもので、五十戸を一郷と定めた。初めは里と云っていたが、霊亀元年(715年)に郷と改めた。この高田郷の名は豊後国志の著者が、豊後風土記に「大分郡、郷玖所」とあるところから、これにならったものであろう。
郷玖所とは、和名抄の郷名に、阿南、植田、津守、荏隈、判太、跡部、武蔵・笠租・笠和・神前の十郷が記録されている。図では、笠和、荏隈判田の三つを郷として、別に植田、戸次、高田、賀来、阿南津守の六つの荘をつけ加えてある。また、国志では笠和、荏隈、賀来、阿南、植田、津守、判田、高田、戸次を記して、私達の郷土が時代により、資料によって跡部郷、高田郷、高田荘と記録されている。
3・高田荘
図田帳に、大分郡の条に高田荘として、次の様に書かれてある。
高田荘二百町 内百八十町 領家城興寺
地頭職三浦介殿 牧村二十町 領家三浦介殿
地頭御家人牧三郎惟行法名念眼 大炊六郎能
重論之
この高田荘が、大体において前に書いた高田郷の後であると考えられる。 大在の志村に今も 「荘境」と呼ばれている所がある。これが高田荘時代の境界線であったと伝えられている。では領家である城興寺はどこにあったかというと、「大宰管内志豊後之四直入郡の章」に「京都九条の北、烏丸の西にあり」と。 「註」藤原教通の子信長(道長の孫)の建立
このようにして考察してみると、高田荘は初め藤原摂関家の荘園であったとみられ、地頭職三浦介は、源頼朝の重臣三浦氏が鎌倉時代に新たに任ぜられたものである。更に高田荘の中には、図 に書かれてあるように牧村がある。これは旧東大分の大字牧で、旧松岡には小牧という所がある。これらから考察してみると高田荘の丘陵地帯には、昔から牧が置かれ、田畑以外の空地に放牧する私牧もあったと考えられる。これは筑前の官牧の記事であるが、右大臣藤原実資の日記である小右記の一部に「治安三年七月十六日 (1023年) 高田牧年貢として絹五十匹、 米七十六石を寄進」(以下略)「万寿二年八月七日(1025年)高田牧年貢を寄進・絹五十匹、米七十石(以下)」とある。現在農業も機械化され農耕馬も見ることができないが、昭和初期までは、中島(現在の高田橋の下流や別保の川原)、松岡の川原等で競馬が行なわれ、常行の首藤家、上徳丸の得丸家等競走馬を飼育していたこと、 大友時代高田豪士が活躍したのもこうした中世からの放牧のなごりではないだろうか。また現在馬に変って乳牛が地区で多く飼育されているのも牧草にめぐまれた自然環境だけでなく、こうした遠い祖先との歴史的環境が物語るのではあるまいか。
4・大友時代の高田
大友氏の始祖能直は、鎮西奉行として、建久七年6月11日(1196年)豊後に入国した。この能直入国の時、これに従って来た御家人の中で、溝口左衛門の尉長繁は高田荘を領して猪野原(今の猪野)に居住した。豊後国志神崎の条に「岩船八幡祀。高田郷横尾村に在り大友能直建久中に建つ。鎌倉鶴岡の神を移して祀る。」これは現在の横尾字若宮に在る若宮八幡(一名 岩船八幡社)である。
地区の大字南鵜ノ鶴にある若宮八幡社(もとは大字丸亀字亀甲にあった)も、その縁起書によると、同じく建久年間に大友能直が創建したとある。(もともとこの両社は初め一社であったかも知れない)
もともと高田荘は藤原摂関家の私荘が京都の城興寺の寺荘となり、鎌倉幕府創立とともにその重臣三浦氏の地頭知行となった。この三浦氏も北条時頼によって討滅され、浦氏も北条時頼によって討滅され、その後城興寺の寺荘として維持されていたが、建武六年(1339年)より十七年後の正平六年十一月二日 (1351年) ならびに同年十二月十九日、足利義詮の下文によると、豊後の守護職大友第八代刑部大輔氏時に与えられた。その後二十二代義統の大友氏滅亡まで或は興り、或はすたれその知行もたびたび変動した様である。およそ荘園は村より成立し、村は名田と在家とから成り立つものである。しかし時代が降るに従って、荘園の知行は小さく分割されるようになって、村または名田畠、或るいは在家の地頭職へと変った。
5・江戸時代の高田
文禄二年(1593年)豊臣秀吉は大友氏を改易すると、改めて検田使を豊後に差遣し、翌三年検地を完了し豊後国全部を直轄地とした。郷土高田はその後徳川家康が天下を平定して慶長六年(1601年)肥後領になるまで徳川氏の直轄であった。領主加藤氏は寛永八年改易され、翌九年小倉城主細川忠利が肥後領五十四万に移封されるに及んで、高田は、明治維新に至るまで細川氏の支配下であった。
石高は、高田村志によると
堂園村 百三十四石七斗余
常行村 二百五十二石三斗余
関門村 二百十六石三斗余
南村 百五十三石一斗余
下徳丸村 三百七十一石六斗余
上徳丸村 二百二十五石七斗余
亀甲村 百三十一石七斗余
鵜ケ瀬村 百九十六石四斗余
大鶴村 百三十五石一斗余
合計 一千八百十六石九斗余
村治の概要
肥後藩では、管内一千八百五十七ヶ村を五十三手永に区画して、各手永に代官兼惣庄屋を置いた。その庄屋が手永内の一切の民政を総管した。豊後の国内には久住、野津原、谷、高田、関の五手永があり、高田は此の中の高田手永に属していた。
当時高田は、いわゆる須賀在八ケ村に分けられて、高田手永代官兼惣屋の支配の下に各村に庄屋、弁差、山ノ口などいう村役人があった。 庄屋は村内の民政を掌る公吏で今日の村長に当り、弁差(一に弁済使とも書く)は小庄屋のことで、今の助役に書記を兼ねたものである。又山ノ口は山林に関する事務を掌るもので高田では、周囲にある壁藪のことを取扱っていた。
以上の外に、別に御家人の中から選任された別度見締役が二人あって、常に村内を巡視して村民の風俗を検察して華奢を戒めた。 戦前の警察官の仕事にあたる。塘方見締といって、土手、山林、渋等の見締をしていた。