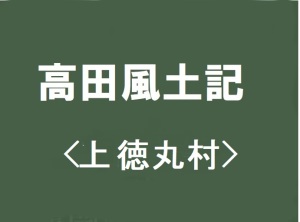高田風土記(訳) 前回のつづき
なお、前回(堂園、常行)の訳は 安部光太郎先生 、関門以降は阿部勝弘氏の訳になります。
読む前に
高田風土記は細川藩が江戸時代の末期に肥後藩領だった高田手永(旧鶴崎市に近い領土)について詳細に調査した報告書です。
その中で高田地区に関係するところを抜粋してみました。
なお、当時高田荘といわれたところは、高田 をはじめ、鶴崎、三佐、桃園、別保、明治、日岡、東大分、大在字志村、川添字迫、鶴村の 1町9ケ 村に亘る地域でした。
高田風土記ついては下記を読んでください。
※青文字で注釈を入れていきたいと思います。
亀甲村
この村に属する、大鶴村と云う小村がある。
郷帳まえは、上徳丸の枝村であったが、今は庄屋は別にある。
亀甲村と大鶴村ともに鶴崎御茶屋から南に位置する。亀甲
村は上徳丸村から西につづく、大鶴村は、鵜猟ヶ瀬の南にあ
って、亀甲村の西にあたり、両方ともに一里ほどである。
○この村は大鶴村につづく平地である。この村の南は土手
沿いであり、土手の外は、大川が流れている。 川を越える
と臼杵領毛井新田村と境になり、西は大鶴村と鵜猟ヶ瀬
との境である。東には上徳丸があり、北は下徳丸と境にな
る。凡そ、東西四丁半・南北三町ほどである。
○大鶴村は南に高い土手がある [この土手は街道の乗り越
しを中にして、東西の川に沿って、須ヶ在の村々を囲う大
きな土手である〕人家は、土手の根付けに続いて平地とな
る場所にある。この村は須ヶ在の端にあり、臼杵領との大
境である〔大境は土手の外東鎧鼻の川辺より南西に小路が
通って標に一本の木がある〕。
南には土手の街道から西に寄ると、畑六反二畝程あって
臼杵領上大津留村の畑地につづく。 東の川向かいに同村
の河原があり境となす。西には西川を越えると臼杵領毛井
村と横尾村と境になる。
凡そ東西三丁半で南北二丁半ほどの地である。
田畑賦税(この項原文のまま)
畑十三丁六反余、高百三十一石七斗余、物成八十五石一斗
余、免は六ツ四分余、
○大鶴村は畑八町八反九畝余、高百三十五石一斗余、物成四
十八石七斗余、免は土手内三ツ六分余、土手外は二ツ一分
余なり。この分は本方にして、この外は両村をつかねて新
地分 高十四石七斗余、畑畝数は新地・諸開畝物等にて四
町四反七畝余りて、上納米十石五斗余・運上銀四十四匁
余なり、御年貢納は前村等に同じ。
土地糞壤
亀甲村の畑地は村の三方面に広がり、大鶴分は村の東方向
にあって、両村とも真土で耕作に適すが、土性は深く堅く耕
すには労する、また こみ士の小砂交じりの和らかな土性で
もあるが、土地浅くて極めて地質が悪い所も多くある。
大鶴の土手沿いの処では、文化元年の洪水によって、土地の
上部を洗い流され、石・砂で浅くなり荒地となって、極めて
悪くなっている。土手の外も是と同じ様に成っている。
○肥料はすべて前の村等に同じである。
戸口牛馬
この村の竈八十七軒、男女四百六十二人、馬二十一疋、 大鶴
村に二十二軒、七十一人、馬四疋あり、
この村の竈で上徳丸の中の土地に住んでいる者十軒、また
大鶴には鵜猟ヶ瀬村の中の土地に居住する十三軒ある。
地士が一人いる。 御郡代直触の者一人この村にまじって
居住する。
○村内の瓦葺蔵四軒ある。土蔵二軒あり、大鶴にも土蔵二軒
ある。
○この村は特高十石から四石までの百姓は十一軒、三石か
ら二石まで二十二軒、その余無高までは五十四軒ある。
大鶴には十石から四石まで四軒あり、三石から二石まで
七軒あり、その余の十一軒は一石から無高までである。
○高畝を人口で割ると、一人につき高 四斗九升余、で畝数
は四畝余にあたる。
課役
この村に助水夫株五人ある。その外大鶴村ともに前の村等
と同じである。
神祠寺院
観音堂の小さな堂が一ヶ所ある。禅宗上徳丸の能仁寺が管理
を受け持つ。
鬼子母神を祀る小堂が大鶴にある。
山林原野
亀甲・大鶴両村土手に沿って人家の間に竹林がある。御藪
畝一町一反が亀甲村にある。大鶴村には一町六反五畝余り
だけである。薪や秣などの事は前の村と同じである。
街道
この村から上徳丸村を通って、鶴崎や百堂の渡しへの道が
通っている。大鶴村へは鵜猟ヶ瀬村を通り、鶴崎から犬飼へ
の街道筋である。
産物
堂園村の内容に同じである。
餘産
この村では大工・木挽き・酒屋を生業としている。又近く
の村で織った縁布や豆などや油粕等を取り次いで売り捌き、(さばき)
或は炭山や材木山に稼ぎに出る者もある。 大鶴村には紺屋
もあり、其の外にも近くの郷に日雇稼ぎに出る者もある。
風俗
この村の生活状態は自立し安定していて富裕の家もある。
他のことでは、堂園の者たちに同じである。
の備へ肝要なる所の義を解きて、ついに是を辞せられし
となり、懸る所ゆへに横塘築き立以来修理怠らず。【以上
は原文のまま】
○鐙鼻に水尺を測る所ありて、洪水の浅深を注進(しん) す。
○本村井戸四十余、大鶴に十三〔深さ水際まで二間から二間
[半まである〕ともに水の勢いは強い。
切れた時 土手を築き直すのに、上土を取ったことで最も小
石まじりの土地になった。
鶏猟ヶ瀬村
亀甲村庄屋が兼勤する
鶴崎御茶屋より南の方角であり、常行村や南村を通って
二十七八丁程隔たっている。
○東は下徳丸村・亀甲村・大鶴村と境に成っている。 南には
大鶴村に境になり、西は西川を挟んで臼杵領横尾村境に
なる。 北は南村・下徳丸村と境になる。 凡そ東西には三丁
半余り、南北六兆余の地である。
田畑賦税(この項原文のまま)
畑十八丁七反六畝余、高百九十六石四斗余、物成百十五石弐
斗余、免は五ツ八分余、此の分は本方にして、此の外新地分
高三石壱斗余、畑畝数は新地・諸開畝物等にて壱丁四反七畝
余、上納米弐石六斗余ありて運上銀弐拾八匁余なり、御年貢
納は前村等に同じ。
土地糞
畑地は多く村の三方面にある。 真土で耕作に適すが、堅く耕
すには労する、また こみ土の砂交じりの和らかな土性でも
が、土地は地質が悪い所も多くある。又土手下の通りはすべ
て小砂まじりで地質は最も悪い。この村の南の通りは大鶴
村に続いており、今まで度々の洪水で土手が切れ石や砂等
が入っており、土地が浅くなっている。 文化元年の土手が
水利
42